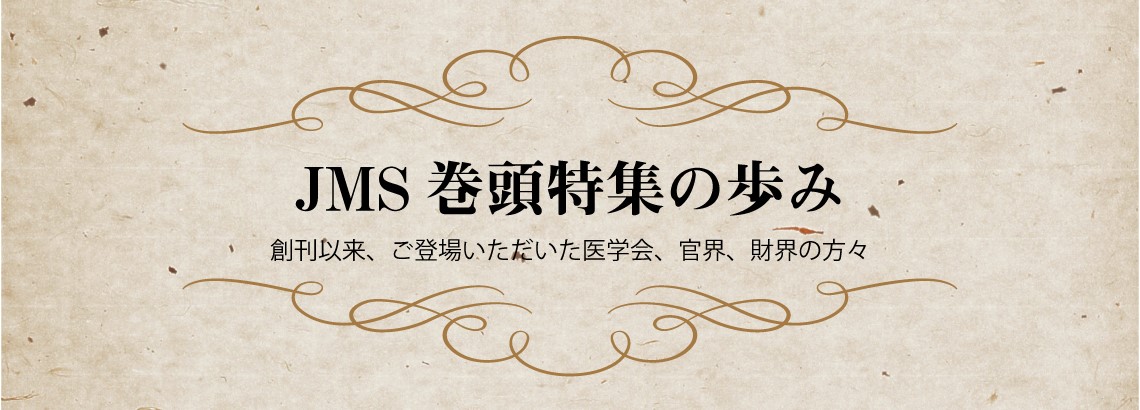
| No. | 特集テーマ | 登場者 ※敬称略・役職は掲載当時のものです |
| 2024年新春号 | 赤十字が繋ぐ人の命、人の尊厳――原点としての人道、その思いを今そして未来へ | 清家篤(日本赤十字社 社長) |
| 2023年10月号 | 岐路に立つiPS 細胞研究――日本発の研究を通して、科学技術立国・日本に今問われていること | 髙橋淳(京都大学iPS 細胞研究所(CiRA)所長) |
| 2023年3月号 | 新生ニッポン!―― 旧弊を打破し、全世代が参加し挑戦する社会へ | 小宮山宏(株式会社三菱総合研究所理事長、一般社団法人プラチナ構想ネットワーク会長、第28 代東京大学総長) |
| 2022年9月号 | 思いやりの心でクルマ社会を生きる―JAF60 年と日本の交通環境を巡って― | 坂口正芳(一般社団法人日本自動車連盟(JAF)会長) |
| 2022年7月号 | パーキンソン病研究で世界を牽引する――組織のトップとして、患者に寄り添う臨床医として | 服部信孝(順天堂大学大学院医学研究科長・医学部長) |
| 2022年3月号/創刊300号 | 人類社会と地球との共存――「新世代の人間の安全保障」への道のり | 武見敬三(参議院議員) |
| 2022年新春号 | 世界の気象・気候変動を考える――二酸化炭素・温暖化・自然災害 | 関田康雄(前・気象庁長官、MS&AD インターリスク総研顧問) |
| 2021年11月号 | コロナ禍から日本の医療を考える――前・日本医師会長として、地域医療の実践者として。 | 横倉義武(前・日本医師会長、ヨコクラ病院理事長) |
| 2021年9月号 | 新型コロナウイルス感染症、総力を挙げた闘い | 尾見茂(新型コロナウイルス感染症対策分科会会長、地域医療機能推進機構(JCHO)理事長) |
| 2021年8月号 | 医の原点に向かって成長する――聖路加での 16 年に寄せて | 福井次矢(聖路加国際病院第10 代院長、京都大学名誉教授) |
| 2021年7月号 | 新型コロナウイルス感染症流行後の我が国の製薬産業 | 武見敬三(参議院議員、参議院自由民主党議員副会長)/中山讓治(日本製薬工業協会前会長) |
| 2021年4月号 | コロナ対策の現状と課題 | 武見敬三(参議院議員)/尾﨑治夫(東京都医師会会長) |
| 2020年9月号 | 混迷からの光明 —コロナ禍に挑む東京都医師会の提言— | 尾﨑治夫(東京都医師会長) |
| 2020年2月号 | The GOLDEN AGER SOCIETY 次世代に繋ぐ正論 (5)—Golden Ager から未来の日本へ— | 江上栄子(江上料理学院院長) |
| 2020年1月号 | The GOLDEN AGER SOCIETY 次世代に繋ぐ正論 (4)—Golden Ager から未来の日本へ— | 山野正義(山野学苑総長) |
| 2019年12月号 | 令和 新時代 私立医大のraison d’etre−日本私立医科大学協会会長就任に寄せて− | 小川彰(日本私立医科大学協会会長、岩手医科大学理事長) |
| 2019年10月号 | The GOLDEN AGER SOCIETY次世代に繋ぐ正論(3)—Golden Ager から未来の日本へ— | 武田隆男(武田病院グループ会長) |
| 2019年8月号 | The GOLDEN AGER SOCIETY次世代に繋ぐ正論(2)—Golden Ager から未来の日本へ— | 藤野武彦(九州大学名誉教授) |
| 2019年7月号 | The GOLDEN AGER SOCIETY次世代に繋ぐ正論(1)—Golden Ager から未来の日本へ— | 野田皆子(全日本美容講師会名誉会長) |
| 2019年4月号 | 列島横断で叶える健康長寿社会―医学・医療の未来を培う日本医学会総会の役割― | 齋藤英彦(第30回日本医学会総会総会2019中部会頭、名古屋大学名誉教授) |
| 2019年2月号 | 医学部新時代―医学部入試を巡る報道の在り方を考える― | 寺野彰(日本私立医科大学協会会長、獨協学園理事長)/小川彰(元全国医学部長病院長会議会長、岩手医科大学理事長) |
| 2018年10月号 | 観光立国日本に向けた医療の役割―現状・課題・施策― | 清野智(JNTO理事長)/寺野彰(国際観光医療学会理事長) |
| 2018年9月号 | JCHOが担う地域医療の未来―地域のニーズに応え、ヘルスケア分野の人材育成を― | 尾身茂(JCHO理事長、名誉WHO西太平洋地域事務局長) |
| 2017年10月号 | 病院における「働き方改革」―医療経営の立場から医師の労働環境を考える― | 福井次矢(聖路加国際病院院長兼聖路加国際大学学長) |
| 2017年9月号 | 日本病院会が推し進める医療改革―発想転換で混迷する現代医療環境を乗り越える― | 相澤孝夫(日本病院会会長) |
| 2017年7月号 | 安全保障から見た日米経済協議 | 武見敬三(参議院議員)/甘利明(衆議院議員) |
| 2016年7月号 | 21世紀成熟国家日本の社会保障 | 武見敬三(参議院議員)/塩崎恭久(厚生労働大臣) |
| 2016年5月号 | 医学部新設の意義をいま問い質す―医師不足解消は既存医学部定員数の調整で可能― | 小川彰(岩手医科大学理事長・学長) |
| 2016年3月号 | 神奈川が革新する超高齢社会 未病対策から健康長寿の実現へ | 黒岩祐治(神奈川県知事)/土屋了介(神奈川県立病院機構理事長) |
| 2015年7月号 | プラズマローゲンで認知症改革 | 藤野武彦(医療法人社団ブックス理事長、九州大学名誉教授) |
| 2015年1月号 | 参加型医療が実現する健康長寿社会 | 井村裕夫(第29回日本医学会総会2015 関西 会頭、先端医療振興財団理事長) |
| 2014年11月号 | 希少糖で糖尿病・肥満対策―香川の希少糖が実現する健康長寿社会― | 近藤浩二(希少糖普及協会代表理事会長)/池田義雄(日本生活習慣病予防協会理事長) |
| 2014年3月号 | 医療教育と医療支援モデルの新たな形 | 小川彰(岩手医科大学理事長・学長) |
| 2014年2月号 | 医療事故調査をめぐる課題と展望 | 古川俊治(参議院議員) |
| 2013年10月号 | わが国の医学教育の課題と私立医科大学の使命 | 寺野彰(日本私立医科大学協会会長、獨協学園理事長、獨協医科大学名誉学長) |
| 2013年8月号 | 日本医師会の歴史的転換―地域医療の再興と医療環境の向上をめざして― | 横倉義武(日本医師会会長) |
| 2013年6月号 | 21世紀におけるわが国の国家像 | 武見敬三(参議院議員)/麻生太郎(副総理兼財務大臣) |
| 2013年5月号 | 健康投資と「熟年パワー」 | 武見敬三(参議院議員) |
| 2012年11月号 | 震災を乗り越え、会津若松の地に最先端医療センターの誕生 | 竹田秀(財団法人竹田綜合病院理事長) |
| 2011年5月号 | 始まったばかりの災害医療 | 石井正三(日本医師会常任理事) |
| 2011年5月号 | 巨大地震でも被害が少なかった宮城県立こども病院の免震構造 | 久道茂(宮城県医療顧問/東北大学名誉教授) |
| 2010年10月号 | 赤十字精神で救う日本の医療と世界の命 | 近衞忠煇(日本赤十字社社長/国際赤十字・赤新月社連盟会長) |
| 2010年4月号 | 良医養成へ 医学教育の課題とは | 栗原敏(東京慈恵会医科大学学長) |
| 2009年5月号 | 医療の未来を映す消化器内視鏡 | 芳野純治(第77回日本消化器内視鏡学会総会会長、藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院院長・消化器内科教授) |
| 2009年4月号 | 薬剤耐性菌との闘い―世界的視野で感染症制御を語る― | 賀来満夫(東北大学大学院医学系研究科 感染制御・検査診断学分野教授) |
| 2009年4月号 | 薬剤耐性菌との闘い―世界的視野で感染症制御を語る― | キャスリン・マーフィー(オーストラリア・ボンド大学准教授/次期APIC会長) |
| 2009年2月号 | 日本における医学教育と医師養成の現状と課題―メディカルスクール実現に向けて | 福井次矢(聖路加国際病院院長) |
| 2009年2月号 | 日本における医学教育と医師養成の現状と課題―メディカルスクール実現に向けて | 日野原重明(聖路加国際病院理事長・名誉院長) |
| 2008年6月号 | 子宮頸がんワクチンの医療経済的考察―女性と国庫を救うために― | 荒川一郎(日本大学薬学部薬事管理学ユニット) |
| 2008年6月号 | 子宮頸がんワクチンの医療経済的考察―女性と国庫を救うために― | 福田敬(東京大学大学院医学系研究科准教授/医療経済研究機構研究部長) |
| 2008年6月号 | 子宮頸がんワクチンの医療経済的考察―女性と国庫を救うために― | 庵原俊昭(国立病院機構三重病院院長・小児科学) |
| 2008年6月号 | 子宮頸がんワクチンの医療経済的考察―女性と国庫を救うために― | 吉川裕之(筑波大学大学院人間総合科学研究科産科婦人周産期医学教授) |
| 2008年1月号 | 医療の質・安全の先にあるもの | ジャック・マッカーシー(ハーバード大学病院リスクマネージメント財団理事長) |
| 2008年1月号 | 医療の質・安全の先にあるもの | 高久史麿(日本医学会会長/医療の質・安全学会理事長/自治医科大学学長) |
| 2007年11月号 | 真に国民のための医療情報電子化へ向けて~医療情報の現状と今後の課題~ | 大井川和彦(マイクロソフト株式会社執行役常務/公共インダストリー統括本部長) |
| 2007年11月号 | 真に国民のための医療情報電子化へ向けて~医療情報の現状と今後の課題~ | 山本隆一(日本医療情報学会理事長・会長/東京大学大学院情報学環准教授) |
| 2007年9月号 | 将来の医師育成と医学教育のあり方~東洋の知恵と西洋科学の調和~ | 大橋俊夫(全国医学部長病院長会議会長/信州大学医学部長) |
| 2007年9月号 | 将来の医師育成と医学教育のあり方~東洋の知恵と西洋科学の調和~ | 松谷有希雄(厚生労働省医政局長) |
| 2007年4月号 | 第27回日本医学会総会大阪開催に向けて「生命と医療の原点―いのち・ひと・夢―」 | 岸本忠三(第27回日本医学会総会会頭) |
| 2007年1月号 | 医療制度のあるべき方向 | 唐澤祥人(日本医師会会長) |
| 2006年3月号 | 西太平洋地域、そしてアジアにおける日本の医療の役割 | 山本修三(日本病院会会長/アジア病院連盟会長) |
| 2006年3月号 | 西太平洋地域、そしてアジアにおける日本の医療の役割 | 尾身茂(WHO西太平洋地域事務局長) |
| 2005年7月号 | 「22世紀医療センター」に向けて―検診・診断と治療、そして研究が連携する新しい医療の姿 | 永井良三(東京大学医学部附属病院院長) |
| 2005年7月号 | 「22世紀医療センター」に向けて―検診・診断と治療、そして研究が連携する新しい医療の姿 | 大友邦(東京大学医学部附属病院放射線科教授) |
| 2005年1/2月号 | 日本の医療制度のあるべき姿 | 尾辻秀久(厚生労働大臣) |
| 2004年9/10月号 | 医薬品・医療機器の新しい未来に向けて | 黒川清(日本学術会議会長) |
| 2004年9/10月号 | 医薬品・医療機器の新しい未来に向けて | 宮島彰(医薬品医療機器総合機構理事長) |
| 2004年7月号 | 第26回国際女医会議開催に寄せて | 大坪公子(第26回国際女医会議広報・出版委員長/三軒茶屋病院院長) |
| 2004年7月号 | 第26回国際女医会議開催に寄せて | 平敷淳子(第26回国際女医会議事務局長/埼玉医科大学教授) |
| 2004年7月号 | 第26回国際女医会議開催に寄せて | 橋本葉子(第26回国際女医会議組織委員長/日本女医会会長) |
| 2004年6月号 | 植松治雄新会長の抱負―医療のあるべき姿 | 植松治雄(日本医師会会長) |
| 2004年4月号 | 21世紀の小児科医の果たす役割―医学の立場から | 小林登(東京大学名誉教授/国立小児病院名誉院長) |
| 2004年4月号 | 21世紀の小児科医の果たす役割―医学の立場から | 桃井真理子(自治医科大学小児科学教授) |
| 2004年2月号 | 新医師臨床研修制度スタートに向けて | 阿部薫(医療研修推進財団理事長) |
| 2004年2月号 | 新医師臨床研修制度スタートに向けて | 上田博三(厚生労働省医政局医事課長) |
| 2004年2月号 | 新医師臨床研修制度スタートに向けて | 北島政樹(慶應義塾大学医学部長) |
| 2004年2月号 | 新医師臨床研修制度スタートに向けて | 矢崎義雄(国立国際医療センター総長) |
| 2004年1月号 | 電子カルテと地域医療連携 | 大橋克洋(東京都医師会理事 大橋産科/婦人科院長) |
| 2004年1月号 | 電子カルテと地域医療連携 | 吉原博幸(京都大学教授・医学部附属病院医療情報部部長) |
| 2003年12月号 | がん研究:基礎から臨床へ | 富永祐民(第62回日本癌学会総会・学術会長/愛知県がんセンター名誉総長) |
| 2003年11月号 | 人にやさしい地球の健康 | 川口雄次(WHO健康開発総合研究センター所長) |
| 2003年9月号 | 統合医療新時代―その課題と展望 | 井村裕夫(総合科学技術会議議員/京都大学前総長/京都大学名誉教授) |
| 2003年9月号 | 統合医療新時代―その課題と展望 | 渥美和彦(日本統合医療学会代表/東京大学名誉教授) |
| 2003年6月号 | 安全な医療と医療の質の向上をめざして | 楠本万里子(日本看護協会常任理事) |
| 2003年6月号 | 安全な医療と医療の質の向上をめざして | 元原利武(日本病院会常任理事医療安全対策委員会委員長) |
| 2003年3月号 | 第26回日本医学会総会開催に寄せて | 杉岡洋一(第26回日本医学会総会会頭/九州労災病院院長/前九州大学総長) |
| 2003年1/2月号 | 医学教育の現状とこれからのあり方 | 神津忠彦(東京女子医科大学医学教育学・消化器内科学教授) |
| 2002年12月号 | がん治療と医の原点 | 海老原敏(国立がんセンター東病院院長) |
| 2002年11月号 | 生活習慣病と二十一世紀の健康づくり~予防の決め手は肥満対策とライフスタイル修正~ | 村勢敏郎(虎の門病院分院分院長) |
| 2002年11月号 | 生活習慣病と二十一世紀の健康づくり~予防の決め手は肥満対策とライフスタイル修正~ | 井上修二(共立女子大学家政学部食物学科教授) |
| 2002年11月号 | 生活習慣病と二十一世紀の健康づくり~予防の決め手は肥満対策とライフスタイル修正~ | 池田義雄(日本生活習慣病予防協会理事長/タニタ体重科学研究所所長) |
| 2002年9/10月号 | 第26回国際内科学会議とこれからの内科医 | 和泉徹(北里大学医学部内科学Ⅱ教授) |
| 2002年9/10月号 | 第26回国際内科学会議とこれからの内科医 | 堀正二(大阪大学大学院医学系研究科病態情報内科学教授) |
| 2002年7月号 | 日本の福祉~今後の方向と課題~ | 京極高宣(日本社会事業大学学長) |
| 2002年5/6月号 | 医薬品開発の歩み~大きく変わりつつある製薬産業の今後~ | アンドリュー・マスカレーナス(日本イーライリリー株式会社 代表取締役社長) |
| 2002年5/6月号 | 医薬品開発の歩み~大きく変わりつつある製薬産業の今後~ | シドニー・トーレル(イーライリリー社 社長・会長兼最高経営責任者) |
| 2002年1/2月号 | 生命科学が開く創薬環境 | 新井賢一(東京大学医科学研究所所長) |
| 2002年1/2月号 | 生命科学が開く創薬環境 | 永山治(日本製薬工業協会会長) |
| 2002年特別号 | 偶然が生んだ血液とのつながり | 坂口力 (厚生労働大臣) |
| 2001年12月号 | 「健康日本21」の推進による新たな時代へ 自立支援の健康づくり | 松田鈴夫(国際医療福祉大学客員教授) |
| 2001年12月号 | 「健康日本21」の推進による新たな時代へ 自立支援の健康づくり | 下田智久(厚生労働省健康局長) |
| 2001年11月号 | 諸悪の根源糖尿病 飽食時代の食生活を考える | 松谷満子(財団法人日本食生活協会会長) |
| 2001年9/10月号 | がん抑圧に向けて―予防・診断・治療と心のケア― | ワット隆子(あけぼの会代表) |
| 2001年9/10月号 | がん征圧に向けて―予防・診断・治療と心のケア― | 寺田雅昭(国立がんセンター総長) |
| 2001年5/6月号 | 古くて新しい病―結核そしてエイズとのかかわり | 島尾忠男(財団法人エイズ予防財団理事長/財団法人結核予防会顧問) |
| 2001年1/2月号 | 今こそ問われる日本―新世紀の医療福祉の在り方― | 曽野綾子(作家/日本財団会長) |
| 2001年3/4月号 | 老人大国日本―世代をつなぐ新老人― | 山田光胤(金匱会診療所長) |
| 2000年10月号 | 内視鏡医学の現状と将来 | 中村孝司(帝京大学医学部第三内科教授) |
| 2000年10月号 | 内視鏡医学の現状と将来 | 丹羽寛文(社団法人日本消化器内視鏡学会理事長/聖マリアンナ医科大学客員教授) |
| 2000年8/9月号 | 少子化社会の明暗 | 藤井龍子(労働省女性局長) |
| 2000年7月号 | 21世紀の健康大国をめざして | 大輪次郎(愛知県医師会会長) |
| 2000年7月号 | 21世紀の健康大国をめざして | 井形昭弘(あいち健康の森健康科学総合センター長/元鹿児島大学学長) |
| 2000年5/6月号 | 患者が求める医師のあるべき姿 | 猿田亨男(慶應義塾大学医学部長) |
| 2000年4月号 | 高度先進医療の意味するもの | 岩井宏方(高度先進医療研究会会長/岩井医療財団理事長) |
| 2000年4月号 | 高度先進医療の意味するもの | 行天良雄(医事評論家) |
| 2000年3月号 | かかりつけ医とは | 宮川政昭(医療法人社団愛政会理事長) |
| 2000年3月号 | かかりつけ医とは | 寺田俊夫(秋田県医師会会長) |
| 2000年3月号 | かかりつけ医とは | 山家健一(大阪府内科医会会長/日本臨床内科医会常任理事) |
| 2000年1/2月号 | 病院機能評価の現状と課題 | 岩崎榮(日本病院管理学会理事長) |
| 2000年1/2月号 | 病院機能評価の現状と課題 | 廣瀬輝夫(KPMGヘルスケアジャパン取締役/元ニューヨーク医科大学外科教授) |
| 1999年12月号 | 二十一世紀に向けた医療制度改革 | 中山耕作(日本病院会会長) |
| 1999年12月号 | 二十一世紀に向けた医療制度改革 | 伊藤雅治(厚生省健康政策局長) |
| 1999年12月号 | 看護と介護 | 南裕子(日本看護協会会長) |
| 1999年11月号 | 看護と介護 | 南裕子(日本看護協会会長) |
| 1999年9/10月号 | 少子化社会を考える | 藤森宗徳(千葉県医師会会長) |
| 1999年9/10月号 | 少子化社会を考える | 天野曄(日本小児科医会会長) |
| 1999年8月号 | 医療と福祉の新しい構造 | 浅田敏雄(東邦大学名誉学長/厚生省医療審議会会長) |
| 1999年7月号 | 医学教育と国際医療 | 鴨下重彦(国立国際医療センター長) |
| 1999年3月号 | 医師と患者の信頼関係を確立する「医師のあるべき姿」 | 末舛恵一(東京都済生会中央病院院長) |
| 1999年3月号 | Preserving the Golden Age of Woman’s Medicine | ナンシー・W・ディッキー(米国医師会会長) |
| 1998年11月号 | 介護保険と少子化問題~少子高齢社会を考える~ | 宝住与一(栃木県医師会会長) |
| 1998年10月号 | 地域医療に役立つ医療情報システム | 安田恒人(宮城県医師会会長) |
| 1998年7月号 | プライマリ・ケアを支援する医療情報システム | 大櫛陽一(東海大学医学部医用工学情報系教授) |
| 1998年7月号 | プライマリ・ケアを支援する医療情報システム | 山崎寛一郎(埼玉県医師会会長) |
| 1998年5/6月号 | 子供達の心と身体の健康を守るために~江戸川区の取り組みから~ | 亘理純平(江戸川区教育委員会指導主事) |
| 1998年5/6月号 | 子供達の心と身体の健康を守るために~江戸川区の取り組みから~ | 小暮堅三(江戸川区医師会会長) |
| 1998年3/4月号 | 医師に役立つ情報提供のあり方 | レイチェル・アーメテイジ(BMJローカルエディションマネージャー) |
| 1998年3/4月号 | 医師に役立つ情報提供のあり方 | モーリス・ロング(BMJディレクター) |
| 1998年1/2月号 | スポーツと健康~長野オリンピックの成功をめざして~ | 小林實(財団法人長野オリンピック冬季競技大会組織委員会事務総長) |
| 1998年1/2月号 | スポーツと健康~長野オリンピックの成功をめざして~ | 森達夫(長野県医師会会長) |
| 1998年1/2月号 | 新時代のより良い医療情報開示に向けて | 開原成允(国立大蔵病院院長) |
| 1998年1/2月号 | 新時代のより良い医療情報開示に向けて | 小池昭彦(日本医師会常任理事) |
| 1997年12月号 Special Edition | 少子高齢社会における子供の健康 | 田中忠一(神奈川県医師会会長) |
| 1997年12月号 Special Edition | 少子高齢社会における子供の健康 | 秋山洋(国立小児病院院長) |
| 1997年9/10月号 | 新世紀を拓く産官学の連携と協働 | 江崎玲於奈(筑波大学学長) |
| 1997年9/10月号 | 新世紀を拓く産官学の連携と協働 | クリストファー・アダム(日本グラクソ株式会社代表取締役社長) |
| 1997年6月号 | 少子高齢社会における保健医療のあり方 | 佐々木健雄(東京都医師会会長) |
| 1997年6月号 | 少子高齢社会における保健医療のあり方 | 原山陽一(東京都衛生局長) |
| 1997年5月号 | より良い医療を築く病院機能評価 | 宮坂雄平(日本医師会常任理事) |
| 1997年5月号 | より良い医療を築く病院機能評価 | 大道久(日本大学医学部教授) |
| 1997年4月号 | 二十一世紀の医療保険の展望 | 西村周三(京都大学経済学部教授) |
| 1997年3月号 | より良い老人医療と介護保険の実現に向けて | 青柳俊(日本医師会常任理事) |
| 1997年3月号 | より良い老人医療と介護保険の実現に向けて | 池上直己(慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授) |
| 1997年1/2月号 | 地域医療と産業医 | 小泉明(産業医科大学学長) |
| 1996年11月号 | 豊かで活力ある高齢社会をめざして―医療保険・介護保険のあるべき姿― | 坪井栄孝(日本医師会会長) |
| 1996年11月号 | 豊かで活力ある高齢社会をめざして―医療保険・介護保険のあるべき姿― | マイケル・R・ライシュ(ハーバード大学公衆衛生大学院教授/武見記念国際保健講座主任) |
| 1996年10月号 | 新世紀の地方分権にみる保健・医療・福祉 | 糸氏英吉(日本医師会副会長) |
| 1996年10月号 | 新世紀の地方分権にみる保健・医療・福祉 | 大森彌(地方分権推進委員会くらしづくり部会長/東海大学教授) |
| 1996年9月号 | 未来の医療を築く医学教育 | 森岡恭彦(日本医師会副会長) |
| 1996年7月号 | 高齢社会のグループ・ケアと在宅ケア | 羽毛田信吾(厚生省老人保健福祉局長) |
| 1996年6月号 | 21世紀の理想の医療・福祉社会の実現を目指して | 豊田章一郎(経済団体連合会会長) |
| 1996年6月号 | 二十一世紀の理想の医療・社会福祉の実現を目指して | 翁久次郎(全国社会福祉協議会会長) |
| 1996年5月号 | 武見敬三が訊く―転換期のヘルス・ポリティクス― | 秀嶋宏(全日本病院協会会長) |
| 1996年4月号 | 明日の医療を考える | 福井光壽(東京都医師会会長) |
| 1996年1/2月号 | 21世紀への医療―少子化時代の育児環境― | 高木俊明(厚生省児童家庭局長) |
| 1996年1/2月号 | 21世紀への医療―少子化時代の育児環境― | 小池麒一郎(日本医師会常任理事) |
| 1995年9/10月号 | 21世紀への医療―医療経営における現状の問題点― | 黒木武弘(社会福祉・医療事業団理事長) |
| 1995年6月号 | 緊急を要する産業廃棄物対策 | 本吉鼎三(日本医師会常任理事) |
| 1995年Special Issue 3/4月号 | 第24回日本医学会総会特別巻頭対談「第24回日本医学会総会に寄せて」 | 飯島宗一(第24回日本医学会総会会頭) |
| 1995年Special Issue 3/4月号 | 第24回日本医学会総会特別巻頭対談「第24回日本医学会総会に寄せて」 | 森亘(日本医学会会長) |
| 1994年12月号 | 21世紀への医療―高齢者と医療・福祉― | 阿部正俊(厚生省老人保健福祉局長) |
| 1994年11月号 | 21世紀への医療―高齢化に伴う地域社会の医療と福祉― | 金平輝子(東京都副知事) |
| 1994年10月号 | 21世紀への医療―地域医療と産業保健活動について― | 村松明仁(労働省労働基準局安全衛生部長) |
| 1994年10月号 | 21世紀への医療―地域医療と産業保健活動について― | 石川高明(日本医師会常任理事) |
| 1994年7号 | 21世紀への医療―少子化問題と育児環境創り― | 小林秀資(厚生省大臣官房審議官) |
| 1994年7号 | 21世紀への医療―少子化問題と育児環境創り― | 矢野亨(日本医師会常任理事) |
| 1994年5号 | 21世紀の医療を考える―医師需給と医療サービスへの道― | 中村努(日本医師会常任理事) |
| 1993年5号 | 21世紀の医療を考える―少産化と超高齢社会の医療― | 白男川史郎(日本医師会副会長) |
| 1993年5号 | 21世紀の医療を考える―少産化と超高齢社会の医療― | 古川貞二郎(厚生事務次官) |
| 1993年4号 | 21世紀の医療を考える | 谷修一(厚生省保健医療局長) |
| 1993年2/3号 | 21世紀の医療を考える | 岡光序治(厚生省薬務局長) |
| 1993年2/3号 | 21世紀の医療を考える | 坂上正道(日本医師会副会長) |
| 1993年創刊号 | 21世紀の医療を考える | 寺松尚(厚生省保健政策局長) |
| 1993年創刊号 | 21世紀の医療を考える | 村瀬敏郎(日本医師会会長) |
![[JMS WEB] 月刊JMSと連動したWEBサイト](https://jmsweb.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/cropped-JMS-WEB-1.png)